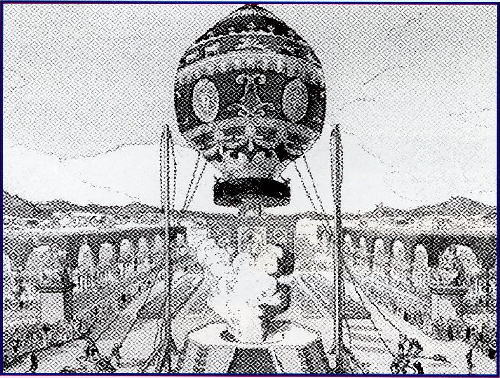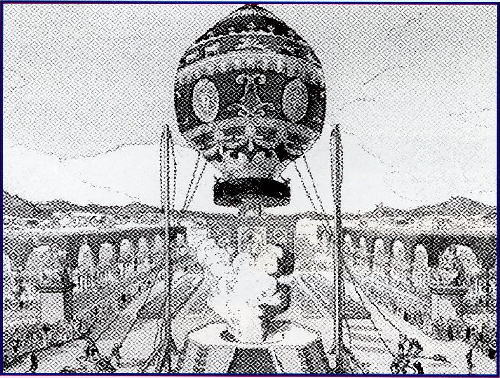熱気球の歴史
熱気球は、フランスのモンゴルフィエ兄弟によって発明された、人類が初めて空中を飛行した乗り物です。
昔々、人が鳥を見て、同じように大空を飛びたいと思っていたことは想像に難くありません。人間の腕に翼のようなものをつけて、鳥と同じように羽ばたくことによって飛行しようとする試みは、ヨ−ロッパの様々な国で数多く記録が残っています。偉大な芸術家で科学者であるレオナルド。ダピンチは、さすがに人間の腕の筋力では、飛行は不可能であることを見抜き、他にパラシュ−トらグライダ−、ヘリコプタ−などの原型のスケッチを残しています。
それから200年くらいたって、1766年にイギリスで空気より軽い気体としての「水素」の分離が成功しました。スコットランドの科学者は、この水素を軽い袋に入れると言うアイデアを思いつきましたが、なぜか実験は行われませんでした。このアイデアは、1783年になってフランスの化学院の緊急指令により急遽実験が開始されました。それは水素と同じように軽い「新ガス」が他で発見されたと言う情報によるものでした。 新ガスは、正体不明でした。この新ガスを紙の袋に入れて浮揚実験に成功したのが、モンゴルフィエ兄弟でした。彼らは、空を飛ぶ道具造りに情熱を注ぎ、紙の袋に空気より軽い気体を閉じ込める研究に没頭していました。空に浮かぶ雲を閉じ込めるため水蒸気の研究も行いました。しかし、水素ガスや、水蒸気を紙の袋に詰めて実験しましたが、なかなかうまく浮かせることができませんでした。ある日、煙が上がる様子を見て、煙を紙袋に閉じ込めることを試みました。暖炉の煙を入れた紙袋は見事に天井まで上昇していきました。この煙の中にこそ「新ガス」成分が含まれていると考えたのでした。
その後、大きく丈夫な袋を作り、何度かの実験を重ね、1783年6月5日に公開実験を行いました。湿った藁を燃やし、煙を袋の下に開いた穴から一杯に吸い込ませ、見事敷成功しました。(この日が熱気球の記念日になっています。)さらに3ケ月後、パリのベルサイユ宮殿前広場で、国王ルイ16世の見守る中、バスケットに羊、アヒル、雄鶏それぞれ1匹づつ乗せて2.4kmの飛行にも成功しました。
そしてついに、1783年11月21日、若者ロジェとダルランド侯爵の2人を乗せたモンゴルフィエ気球は、ブロ−ニュの森から浮上しました。人類が初めて空中を飛行した瞬間です。気球は90mの高度で25分間飛行したと記録されています。フランス語では、今でも熱気球のことを「モンゴルフィエ」と言います。
気球の発明から120年経って、ライト兄弟による飛行機が発明されました。世界大戦を通じて飛行機の時代となり、熱気球のようなのんびりした乗り物の時代は終わりを告げたかのように思われました。しかし、熱気球は再び近代スカイスポ−ツとして大空に登場しました。
日本では、古くは明治時代「西南の役」で軍用として実験製作され、その後は外国からの気球デモンストレ−ションが行われたりしました。アメリカ本土が唯一攻撃を受けたのは、日本の風船爆弾でした。
国際航空連盟では空を飛ぶ人工物体を「航空宇宙機」と呼び、これをクラスAからSまでの17クラスに分類しています。クラsAは自由気球、最後のクラスは放送衛星等の無人宇宙船です。クラス分けは空の歴史を尊重しているので、熱気球は空を飛ぶ物体として、航空宇宙機の先頭クラスにランクされているのです。
日本のスカイスポ−ツとしての熱気球は、1969年京都のイカロス昇天グル−プと北海道大学探検部が共同制作した「イカロス5号」による北海道での飛行から始まりました。手作りの気球製作が盛んに行われた時期もありましたが、現在では、海外の気球専門メ−カ−による高い技術で製作された輸入機材が数多く使用されており、気球愛好者も増加しました。現在、600機以上の熱気球が日本気球連盟に登録されています。